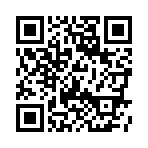2017年09月22日
イオングランドオープンと交通状況、ほか、もろもろ。
気まぐれに出現する、いち、松本人の本音。
今日はやはり、イオンモールについて。
タウンスニーカーの大幅な増便にて、際立った渋滞も起こっていないとのニュースだが、実際はどうなのか。
16日のソフトオープン(渋滞緩和のためのローカルに向けたプレオープンでした)に続き、21日グランドオープンを過ぎた今日、お昼休みに電車どおりを通ってみた。
平日ということもあるか、普段と変わらない状況。
いそいそと歩く人々を「きっとイオンに行くんだ」と勝手な想像をしながら、源智の井戸近くのパン屋さんに到着。
で、やっぱり話題になるのはイオンだが、立ち話したところ、確かに午前中はそれらしい人が増えたが、道が混雑したとか、そういう困った状況はまだ無いそう。
むしろ、午後は、衣料品やイオンスタイルのある「晴庭」から帰る人たちは中町を通ってゆくらしく、いつもどおりの日常が続いている。
しかもグランドオープンした後の週末はうまく歩行者天国が続いてますよね、と言われて、数えてみると、
★9月23日(土・祝) 2017松本ノーマイカーデー
★10月1日(日) 第1回松本マラソン
★そば祭りで、大名町通り歩行者天国: 10月8日(日)・9日(月・祝)10:00~16:00予定
あ、本当だ。けっこうあった。
だから、本格的な勝負は寒くて車の移動が多くなってくる冬場ではないかと。
しかし、あがたの森でイベントがあるときは、どうなるのか。
10月にはクラフトピクニック、いちばんは来年の5月開催のクラフトフェア。
すこし買い物客の波も落ち着いてくれれば良いけど、1年の松本イベントをすべてやり終えないと、渋滞緩和は大丈夫だったかは言い切れない気がしてきた。
そんなことを考えながら、夕方の帰り道。
中町を南北に抜けて、ナワテに行こうとしたら、あれ、混んでる!!
雨の日、中町通りを西から東へ抜ける車が渋滞することはあっても、それより一本北の川沿いは車の量すら少なかったのに、どんどん東から車が流れてくる・・・。というか目の前で停滞し始める。
車の流れ着く先の大名町・本町は普段から帰宅ラッシュで混んでるから、さらに渋滞。
南北に通り過ぎることすら、すんなりといかない状況で、パン屋さんの「帰りは中町を抜けるようだ」が、こういうことだったのか・・・と実感した。
やっぱり。。。
イオンには、地元も市外の人も、公共交通機関や力車(市の無料レンタルチャリ)、徒歩で行くのが良いようだ。
よくヨーロッパの人はたくさん歩くと聞くけれども、松本も、健康寿命延伸都市として、「買い物も歩く」 が定着すればと思う。
秋のイベント盛りだくさんの時期を越えると、どことなく物寂しくなる松本の町。
寒風の中でも、人が多く歩いていれば、きっとお店も空気も華やぐ。
そんなんで、ここのブログでは、新たに「イオンから徒歩・チャリ圏内」の店カテゴリーを作ってみようかと・・・。
「歩く」買い物の誘発になればいいなと、少しだけ、本気で考えてみた。
今日はやはり、イオンモールについて。
タウンスニーカーの大幅な増便にて、際立った渋滞も起こっていないとのニュースだが、実際はどうなのか。
16日のソフトオープン(渋滞緩和のためのローカルに向けたプレオープンでした)に続き、21日グランドオープンを過ぎた今日、お昼休みに電車どおりを通ってみた。
平日ということもあるか、普段と変わらない状況。
いそいそと歩く人々を「きっとイオンに行くんだ」と勝手な想像をしながら、源智の井戸近くのパン屋さんに到着。
で、やっぱり話題になるのはイオンだが、立ち話したところ、確かに午前中はそれらしい人が増えたが、道が混雑したとか、そういう困った状況はまだ無いそう。
むしろ、午後は、衣料品やイオンスタイルのある「晴庭」から帰る人たちは中町を通ってゆくらしく、いつもどおりの日常が続いている。
しかもグランドオープンした後の週末はうまく歩行者天国が続いてますよね、と言われて、数えてみると、
★9月23日(土・祝) 2017松本ノーマイカーデー
★10月1日(日) 第1回松本マラソン
★そば祭りで、大名町通り歩行者天国: 10月8日(日)・9日(月・祝)10:00~16:00予定
あ、本当だ。けっこうあった。
だから、本格的な勝負は寒くて車の移動が多くなってくる冬場ではないかと。
しかし、あがたの森でイベントがあるときは、どうなるのか。
10月にはクラフトピクニック、いちばんは来年の5月開催のクラフトフェア。
すこし買い物客の波も落ち着いてくれれば良いけど、1年の松本イベントをすべてやり終えないと、渋滞緩和は大丈夫だったかは言い切れない気がしてきた。
そんなことを考えながら、夕方の帰り道。
中町を南北に抜けて、ナワテに行こうとしたら、あれ、混んでる!!
雨の日、中町通りを西から東へ抜ける車が渋滞することはあっても、それより一本北の川沿いは車の量すら少なかったのに、どんどん東から車が流れてくる・・・。というか目の前で停滞し始める。
車の流れ着く先の大名町・本町は普段から帰宅ラッシュで混んでるから、さらに渋滞。
南北に通り過ぎることすら、すんなりといかない状況で、パン屋さんの「帰りは中町を抜けるようだ」が、こういうことだったのか・・・と実感した。
やっぱり。。。
イオンには、地元も市外の人も、公共交通機関や力車(市の無料レンタルチャリ)、徒歩で行くのが良いようだ。
よくヨーロッパの人はたくさん歩くと聞くけれども、松本も、健康寿命延伸都市として、「買い物も歩く」 が定着すればと思う。
秋のイベント盛りだくさんの時期を越えると、どことなく物寂しくなる松本の町。
寒風の中でも、人が多く歩いていれば、きっとお店も空気も華やぐ。
そんなんで、ここのブログでは、新たに「イオンから徒歩・チャリ圏内」の店カテゴリーを作ってみようかと・・・。
「歩く」買い物の誘発になればいいなと、少しだけ、本気で考えてみた。
2014年11月02日
松本山雅J1昇格。
昨日はどのくらいの山雅ファンが福岡を目指していたのか。
あるいは、中継を見ていたのか。
「山雅の応援って面白いの? 一度も行ったことがない」と試合前日話している松本市民も、
話題にするくらいなら、どことなくJ1昇格は気にはなっていたかと思います。
そして熱狂の翌日。
信濃毎日新聞、市民タイムスの両面1面、最高の計らいでしたね!
今日の新聞を読んで改めて実感がわいてきましたが、
我が家の贔屓は田中隼磨選手。
(うちの子どもは、「はゆま」が言いにくいらしく、「はいま」と呼んでます)
地元出身だし、J1チームから来てもらったし、3番だし。
この一年間、嫌でも周囲の期待を感じただろうし、
責任感やプレッシャーはとても大きかったと思うのです。
「ありがとう松田」の白Tシャツ。
新聞でもう一度見たとき、また涙が出そうになりました。
去年、プレーオフにかかるか、かからないかだったのに、
たった1年で自動昇格。
今年はプレーオフにはいれば上出来だと思っていたのに驚くほどのスピード昇格。
なんだか、夢物語の中に今だいるようです。
されどJ1昇格はあくまでスタートライン。
たくさんの喜びの一方で、新聞が多方面から伝えるように
「アルウィン改修待ったなし」など新たな問題も浮上しています。
たとえば今、松本城を世界遺産に・・・って運動もあるけど、
もし世界遺産になったら、今の松本市はそれだけ多言語に対応できている施設やお店はあるのか、
交通機能はどうなるのか、
恥ずかしがり屋の長野県民が、どの程度おもてなし心を発揮できるのか、
そして私たち市民はこれまで通り、快適に生活を維持できるのか。。。
考えただけで「まだ無理。」と思います。
山雅もちょっとそれに似たところがあります。
でも。
松本城も旧開智学校も、松本に住む人たちが危機感を感じて創り守り続けてきました。
そんな風土だから、松本山雅についても何とか解決していくんじゃないかと感じます。
松本山雅J1昇格のニュースは新たなる街づくりの問題提起でもあり、
松本に流れてる町人気質の血を滾らせるようなものを感じました。
今日も、普通に図書館に行って、サビア選手のしおりをもらい、ウハウハ喜ぶ子どもたち。
ほぼ日常は変わりません。
たぶん、J1になっても、アルウィンは人が増えるだけで雰囲気は変わらないでしょう。
“地元だから” その理由で、ゆるく、和やかに、必要があれば時に熱く。
これからはそこに “支えていくんだ” という気持ちを少し持てば、
きっと大きな問題も解決していくのだと思います。
松本のチーム、山雅。
これからも“地元だから” ずっと応援していきます。
あるいは、中継を見ていたのか。
「山雅の応援って面白いの? 一度も行ったことがない」と試合前日話している松本市民も、
話題にするくらいなら、どことなくJ1昇格は気にはなっていたかと思います。
そして熱狂の翌日。
信濃毎日新聞、市民タイムスの両面1面、最高の計らいでしたね!
今日の新聞を読んで改めて実感がわいてきましたが、
我が家の贔屓は田中隼磨選手。
(うちの子どもは、「はゆま」が言いにくいらしく、「はいま」と呼んでます)
地元出身だし、J1チームから来てもらったし、3番だし。
この一年間、嫌でも周囲の期待を感じただろうし、
責任感やプレッシャーはとても大きかったと思うのです。
「ありがとう松田」の白Tシャツ。
新聞でもう一度見たとき、また涙が出そうになりました。
去年、プレーオフにかかるか、かからないかだったのに、
たった1年で自動昇格。
今年はプレーオフにはいれば上出来だと思っていたのに驚くほどのスピード昇格。
なんだか、夢物語の中に今だいるようです。
されどJ1昇格はあくまでスタートライン。
たくさんの喜びの一方で、新聞が多方面から伝えるように
「アルウィン改修待ったなし」など新たな問題も浮上しています。
たとえば今、松本城を世界遺産に・・・って運動もあるけど、
もし世界遺産になったら、今の松本市はそれだけ多言語に対応できている施設やお店はあるのか、
交通機能はどうなるのか、
恥ずかしがり屋の長野県民が、どの程度おもてなし心を発揮できるのか、
そして私たち市民はこれまで通り、快適に生活を維持できるのか。。。
考えただけで「まだ無理。」と思います。
山雅もちょっとそれに似たところがあります。
でも。
松本城も旧開智学校も、松本に住む人たちが危機感を感じて創り守り続けてきました。
そんな風土だから、松本山雅についても何とか解決していくんじゃないかと感じます。
松本山雅J1昇格のニュースは新たなる街づくりの問題提起でもあり、
松本に流れてる町人気質の血を滾らせるようなものを感じました。
今日も、普通に図書館に行って、サビア選手のしおりをもらい、ウハウハ喜ぶ子どもたち。
ほぼ日常は変わりません。
たぶん、J1になっても、アルウィンは人が増えるだけで雰囲気は変わらないでしょう。
“地元だから” その理由で、ゆるく、和やかに、必要があれば時に熱く。
これからはそこに “支えていくんだ” という気持ちを少し持てば、
きっと大きな問題も解決していくのだと思います。
松本のチーム、山雅。
これからも“地元だから” ずっと応援していきます。
2014年05月11日
あらためて、松本。
"3ガク都市”、まつもと。
ご存知のとおり、3つの"ガク”とは、“学”問、音“楽”、山“岳” のことです。
松本市外・県外でも生活をしここに戻ってきてし、あらためて実感したこと。
それは、この3つの“ガク”が単なる観光的な標榜だけでないという、体験です。
まず音楽の“学”。
市民が音楽について、聞く耳を持っている・・・というか、
音楽について寛容です。
例えば集合住宅などの場合、ちょっとでも楽器の音がなれば
「うるさい」と苦情や管理者からやめるよう通達が来たりしますが、
松本では、あまり音楽の練習で苦情になったとか、そういった話を聞きません。
県外から引っ越してきた人も、
外を歩いていると、楽器の音が普通に聞こえてきた、とちょっと驚きと感動が混じるくらい。
各学校にブラスバンドがあるのは当たり前。
スズキメソードの本拠地ともあって、音楽を経験している人は沢山いるはず。
だから地元の人は、楽器の音を聞くと、
「練習がんばってるなぁ」とむしろ微笑ましく感じます。
逆に松本市ではバイオリンの練習が自宅にできていたいたのに、
市外へ引っ越したら苦情が来てできなくなった、という話も聞きます。
松本サイトウキネンフェスティバルやスズキメソードの本拠地で有名、という
わけではなさそう・・・なのです。
次に山岳の“岳”。
映画化された漫画“岳”にも何度か松本駅が登場するように、
松本市は北アルプスの玄関口です。
国の特別名勝かつ特別天然記念物である、上高地はここ松本市にあります。
私は山に積極的に登らないので深いことはいえませんが、
市内を歩いていると、登山者らしい格好の方をちらほら見かけるし、
春になれば、山菜摂りだ、秋はキノコだ、冬はスキーだと、
レジャーとしても山は松本市民にとって身近な存在です。
そして、長野といえば、国立信州大学。
ここでは山岳という地域性を生かして、高緯度の環境が生物にどう影響するかなど、
高度な医療と結び付ける特徴的な研究がなされています。
そんなわけで、海外から留学に来る人も多く、海外の医療で学んで、
またここ松本で、その知識と技術を深めている人も多く、
“岳”というものを通して、地方なのにとても国際的な都市が、まつもとです。
最後に学ぶの“学”。
生涯学習都市、まつもと、とという方針だけあり、
市立図書館が生活圏の中に利用しやすい位置に配置され、
小さくとも町中に博物館が点在します。
そもそも、今の信大などのもとになっている
旧開智学校は、市民の寄付によって建設されました。
松本城も、古くなり傾いていた天守を、このままではいけない、
という思いを抱いた人が買い取り、寄付を集め、
大改修ののち、今の国宝に繋がっています。
“教育県ながの”とよく言われますが、
全国平均から見て、学力はそれほど高くありません。
じゃぁ、なにが教育県、なのか・・・というと、
自分から学び取る力、学ぶ姿勢を育てる力、
つまり、『生涯学習力』が昔から育っているわけです。
男子高、女子高、共学、
それぞれの設立の歴史を受け継ぎ、
学力ランク付けのみでは終わらない、特色ある4つの県立高校。
県立高校と同様に、歴史があり地域に根ざしてきた私立高校。
そんな歴史と環境が、
まつもとで育つ人に、地域への誇りと愛着を育てているように感じます。
ボランティアが関わることが当たり前のようになっている、イベントごと各種。
クラフトフェアや、大歌舞伎、大道芸、サイトウキネン、松本山雅などなど。
地域のことだから自分たちで何とかしよう、という自己解決力と、
松本城下町、商人の町、おまつり好きの血が相まって、
良い感じに作用しているのではないでしょうか。
サッカー王国でもないのに、
松本山雅サポーターがどっと集まる不思議。
サッカーファンはもとより、
孫を連れてくるおじいちゃんや、家族連れの観戦者が多いのを見ると、
そこには、サッカーを見る行為を一種のスタイル的に捉えているのではなく、
「まつもとのチームだから当然応援する」「まつもとに来てくれてありがとう」といった、
地元愛にあふれた雰囲気、
まさにまつもと市民の特徴を端的に表しているとも言えます。
子どもの頃には日常で気付かなかったまつもとの魅力。
他を見てきて、大人になったからこそ知り得た、大切に伝えたいものが
たくさんあります。
ご存知のとおり、3つの"ガク”とは、“学”問、音“楽”、山“岳” のことです。
松本市外・県外でも生活をしここに戻ってきてし、あらためて実感したこと。
それは、この3つの“ガク”が単なる観光的な標榜だけでないという、体験です。
まず音楽の“学”。
市民が音楽について、聞く耳を持っている・・・というか、
音楽について寛容です。
例えば集合住宅などの場合、ちょっとでも楽器の音がなれば
「うるさい」と苦情や管理者からやめるよう通達が来たりしますが、
松本では、あまり音楽の練習で苦情になったとか、そういった話を聞きません。
県外から引っ越してきた人も、
外を歩いていると、楽器の音が普通に聞こえてきた、とちょっと驚きと感動が混じるくらい。
各学校にブラスバンドがあるのは当たり前。
スズキメソードの本拠地ともあって、音楽を経験している人は沢山いるはず。
だから地元の人は、楽器の音を聞くと、
「練習がんばってるなぁ」とむしろ微笑ましく感じます。
逆に松本市ではバイオリンの練習が自宅にできていたいたのに、
市外へ引っ越したら苦情が来てできなくなった、という話も聞きます。
松本サイトウキネンフェスティバルやスズキメソードの本拠地で有名、という
わけではなさそう・・・なのです。
次に山岳の“岳”。
映画化された漫画“岳”にも何度か松本駅が登場するように、
松本市は北アルプスの玄関口です。
国の特別名勝かつ特別天然記念物である、上高地はここ松本市にあります。
私は山に積極的に登らないので深いことはいえませんが、
市内を歩いていると、登山者らしい格好の方をちらほら見かけるし、
春になれば、山菜摂りだ、秋はキノコだ、冬はスキーだと、
レジャーとしても山は松本市民にとって身近な存在です。
そして、長野といえば、国立信州大学。
ここでは山岳という地域性を生かして、高緯度の環境が生物にどう影響するかなど、
高度な医療と結び付ける特徴的な研究がなされています。
そんなわけで、海外から留学に来る人も多く、海外の医療で学んで、
またここ松本で、その知識と技術を深めている人も多く、
“岳”というものを通して、地方なのにとても国際的な都市が、まつもとです。
最後に学ぶの“学”。
生涯学習都市、まつもと、とという方針だけあり、
市立図書館が生活圏の中に利用しやすい位置に配置され、
小さくとも町中に博物館が点在します。
そもそも、今の信大などのもとになっている
旧開智学校は、市民の寄付によって建設されました。
松本城も、古くなり傾いていた天守を、このままではいけない、
という思いを抱いた人が買い取り、寄付を集め、
大改修ののち、今の国宝に繋がっています。
“教育県ながの”とよく言われますが、
全国平均から見て、学力はそれほど高くありません。
じゃぁ、なにが教育県、なのか・・・というと、
自分から学び取る力、学ぶ姿勢を育てる力、
つまり、『生涯学習力』が昔から育っているわけです。
男子高、女子高、共学、
それぞれの設立の歴史を受け継ぎ、
学力ランク付けのみでは終わらない、特色ある4つの県立高校。
県立高校と同様に、歴史があり地域に根ざしてきた私立高校。
そんな歴史と環境が、
まつもとで育つ人に、地域への誇りと愛着を育てているように感じます。
ボランティアが関わることが当たり前のようになっている、イベントごと各種。
クラフトフェアや、大歌舞伎、大道芸、サイトウキネン、松本山雅などなど。
地域のことだから自分たちで何とかしよう、という自己解決力と、
松本城下町、商人の町、おまつり好きの血が相まって、
良い感じに作用しているのではないでしょうか。
サッカー王国でもないのに、
松本山雅サポーターがどっと集まる不思議。
サッカーファンはもとより、
孫を連れてくるおじいちゃんや、家族連れの観戦者が多いのを見ると、
そこには、サッカーを見る行為を一種のスタイル的に捉えているのではなく、
「まつもとのチームだから当然応援する」「まつもとに来てくれてありがとう」といった、
地元愛にあふれた雰囲気、
まさにまつもと市民の特徴を端的に表しているとも言えます。
子どもの頃には日常で気付かなかったまつもとの魅力。
他を見てきて、大人になったからこそ知り得た、大切に伝えたいものが
たくさんあります。