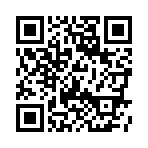2014年05月11日
あらためて、松本。
"3ガク都市”、まつもと。
ご存知のとおり、3つの"ガク”とは、“学”問、音“楽”、山“岳” のことです。
松本市外・県外でも生活をしここに戻ってきてし、あらためて実感したこと。
それは、この3つの“ガク”が単なる観光的な標榜だけでないという、体験です。
まず音楽の“学”。
市民が音楽について、聞く耳を持っている・・・というか、
音楽について寛容です。
例えば集合住宅などの場合、ちょっとでも楽器の音がなれば
「うるさい」と苦情や管理者からやめるよう通達が来たりしますが、
松本では、あまり音楽の練習で苦情になったとか、そういった話を聞きません。
県外から引っ越してきた人も、
外を歩いていると、楽器の音が普通に聞こえてきた、とちょっと驚きと感動が混じるくらい。
各学校にブラスバンドがあるのは当たり前。
スズキメソードの本拠地ともあって、音楽を経験している人は沢山いるはず。
だから地元の人は、楽器の音を聞くと、
「練習がんばってるなぁ」とむしろ微笑ましく感じます。
逆に松本市ではバイオリンの練習が自宅にできていたいたのに、
市外へ引っ越したら苦情が来てできなくなった、という話も聞きます。
松本サイトウキネンフェスティバルやスズキメソードの本拠地で有名、という
わけではなさそう・・・なのです。
次に山岳の“岳”。
映画化された漫画“岳”にも何度か松本駅が登場するように、
松本市は北アルプスの玄関口です。
国の特別名勝かつ特別天然記念物である、上高地はここ松本市にあります。
私は山に積極的に登らないので深いことはいえませんが、
市内を歩いていると、登山者らしい格好の方をちらほら見かけるし、
春になれば、山菜摂りだ、秋はキノコだ、冬はスキーだと、
レジャーとしても山は松本市民にとって身近な存在です。
そして、長野といえば、国立信州大学。
ここでは山岳という地域性を生かして、高緯度の環境が生物にどう影響するかなど、
高度な医療と結び付ける特徴的な研究がなされています。
そんなわけで、海外から留学に来る人も多く、海外の医療で学んで、
またここ松本で、その知識と技術を深めている人も多く、
“岳”というものを通して、地方なのにとても国際的な都市が、まつもとです。
最後に学ぶの“学”。
生涯学習都市、まつもと、とという方針だけあり、
市立図書館が生活圏の中に利用しやすい位置に配置され、
小さくとも町中に博物館が点在します。
そもそも、今の信大などのもとになっている
旧開智学校は、市民の寄付によって建設されました。
松本城も、古くなり傾いていた天守を、このままではいけない、
という思いを抱いた人が買い取り、寄付を集め、
大改修ののち、今の国宝に繋がっています。
“教育県ながの”とよく言われますが、
全国平均から見て、学力はそれほど高くありません。
じゃぁ、なにが教育県、なのか・・・というと、
自分から学び取る力、学ぶ姿勢を育てる力、
つまり、『生涯学習力』が昔から育っているわけです。
男子高、女子高、共学、
それぞれの設立の歴史を受け継ぎ、
学力ランク付けのみでは終わらない、特色ある4つの県立高校。
県立高校と同様に、歴史があり地域に根ざしてきた私立高校。
そんな歴史と環境が、
まつもとで育つ人に、地域への誇りと愛着を育てているように感じます。
ボランティアが関わることが当たり前のようになっている、イベントごと各種。
クラフトフェアや、大歌舞伎、大道芸、サイトウキネン、松本山雅などなど。
地域のことだから自分たちで何とかしよう、という自己解決力と、
松本城下町、商人の町、おまつり好きの血が相まって、
良い感じに作用しているのではないでしょうか。
サッカー王国でもないのに、
松本山雅サポーターがどっと集まる不思議。
サッカーファンはもとより、
孫を連れてくるおじいちゃんや、家族連れの観戦者が多いのを見ると、
そこには、サッカーを見る行為を一種のスタイル的に捉えているのではなく、
「まつもとのチームだから当然応援する」「まつもとに来てくれてありがとう」といった、
地元愛にあふれた雰囲気、
まさにまつもと市民の特徴を端的に表しているとも言えます。
子どもの頃には日常で気付かなかったまつもとの魅力。
他を見てきて、大人になったからこそ知り得た、大切に伝えたいものが
たくさんあります。
ご存知のとおり、3つの"ガク”とは、“学”問、音“楽”、山“岳” のことです。
松本市外・県外でも生活をしここに戻ってきてし、あらためて実感したこと。
それは、この3つの“ガク”が単なる観光的な標榜だけでないという、体験です。
まず音楽の“学”。
市民が音楽について、聞く耳を持っている・・・というか、
音楽について寛容です。
例えば集合住宅などの場合、ちょっとでも楽器の音がなれば
「うるさい」と苦情や管理者からやめるよう通達が来たりしますが、
松本では、あまり音楽の練習で苦情になったとか、そういった話を聞きません。
県外から引っ越してきた人も、
外を歩いていると、楽器の音が普通に聞こえてきた、とちょっと驚きと感動が混じるくらい。
各学校にブラスバンドがあるのは当たり前。
スズキメソードの本拠地ともあって、音楽を経験している人は沢山いるはず。
だから地元の人は、楽器の音を聞くと、
「練習がんばってるなぁ」とむしろ微笑ましく感じます。
逆に松本市ではバイオリンの練習が自宅にできていたいたのに、
市外へ引っ越したら苦情が来てできなくなった、という話も聞きます。
松本サイトウキネンフェスティバルやスズキメソードの本拠地で有名、という
わけではなさそう・・・なのです。
次に山岳の“岳”。
映画化された漫画“岳”にも何度か松本駅が登場するように、
松本市は北アルプスの玄関口です。
国の特別名勝かつ特別天然記念物である、上高地はここ松本市にあります。
私は山に積極的に登らないので深いことはいえませんが、
市内を歩いていると、登山者らしい格好の方をちらほら見かけるし、
春になれば、山菜摂りだ、秋はキノコだ、冬はスキーだと、
レジャーとしても山は松本市民にとって身近な存在です。
そして、長野といえば、国立信州大学。
ここでは山岳という地域性を生かして、高緯度の環境が生物にどう影響するかなど、
高度な医療と結び付ける特徴的な研究がなされています。
そんなわけで、海外から留学に来る人も多く、海外の医療で学んで、
またここ松本で、その知識と技術を深めている人も多く、
“岳”というものを通して、地方なのにとても国際的な都市が、まつもとです。
最後に学ぶの“学”。
生涯学習都市、まつもと、とという方針だけあり、
市立図書館が生活圏の中に利用しやすい位置に配置され、
小さくとも町中に博物館が点在します。
そもそも、今の信大などのもとになっている
旧開智学校は、市民の寄付によって建設されました。
松本城も、古くなり傾いていた天守を、このままではいけない、
という思いを抱いた人が買い取り、寄付を集め、
大改修ののち、今の国宝に繋がっています。
“教育県ながの”とよく言われますが、
全国平均から見て、学力はそれほど高くありません。
じゃぁ、なにが教育県、なのか・・・というと、
自分から学び取る力、学ぶ姿勢を育てる力、
つまり、『生涯学習力』が昔から育っているわけです。
男子高、女子高、共学、
それぞれの設立の歴史を受け継ぎ、
学力ランク付けのみでは終わらない、特色ある4つの県立高校。
県立高校と同様に、歴史があり地域に根ざしてきた私立高校。
そんな歴史と環境が、
まつもとで育つ人に、地域への誇りと愛着を育てているように感じます。
ボランティアが関わることが当たり前のようになっている、イベントごと各種。
クラフトフェアや、大歌舞伎、大道芸、サイトウキネン、松本山雅などなど。
地域のことだから自分たちで何とかしよう、という自己解決力と、
松本城下町、商人の町、おまつり好きの血が相まって、
良い感じに作用しているのではないでしょうか。
サッカー王国でもないのに、
松本山雅サポーターがどっと集まる不思議。
サッカーファンはもとより、
孫を連れてくるおじいちゃんや、家族連れの観戦者が多いのを見ると、
そこには、サッカーを見る行為を一種のスタイル的に捉えているのではなく、
「まつもとのチームだから当然応援する」「まつもとに来てくれてありがとう」といった、
地元愛にあふれた雰囲気、
まさにまつもと市民の特徴を端的に表しているとも言えます。
子どもの頃には日常で気付かなかったまつもとの魅力。
他を見てきて、大人になったからこそ知り得た、大切に伝えたいものが
たくさんあります。
Posted by 鉄腕 at 13:21│Comments(0)
│■『松本』について考える。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。